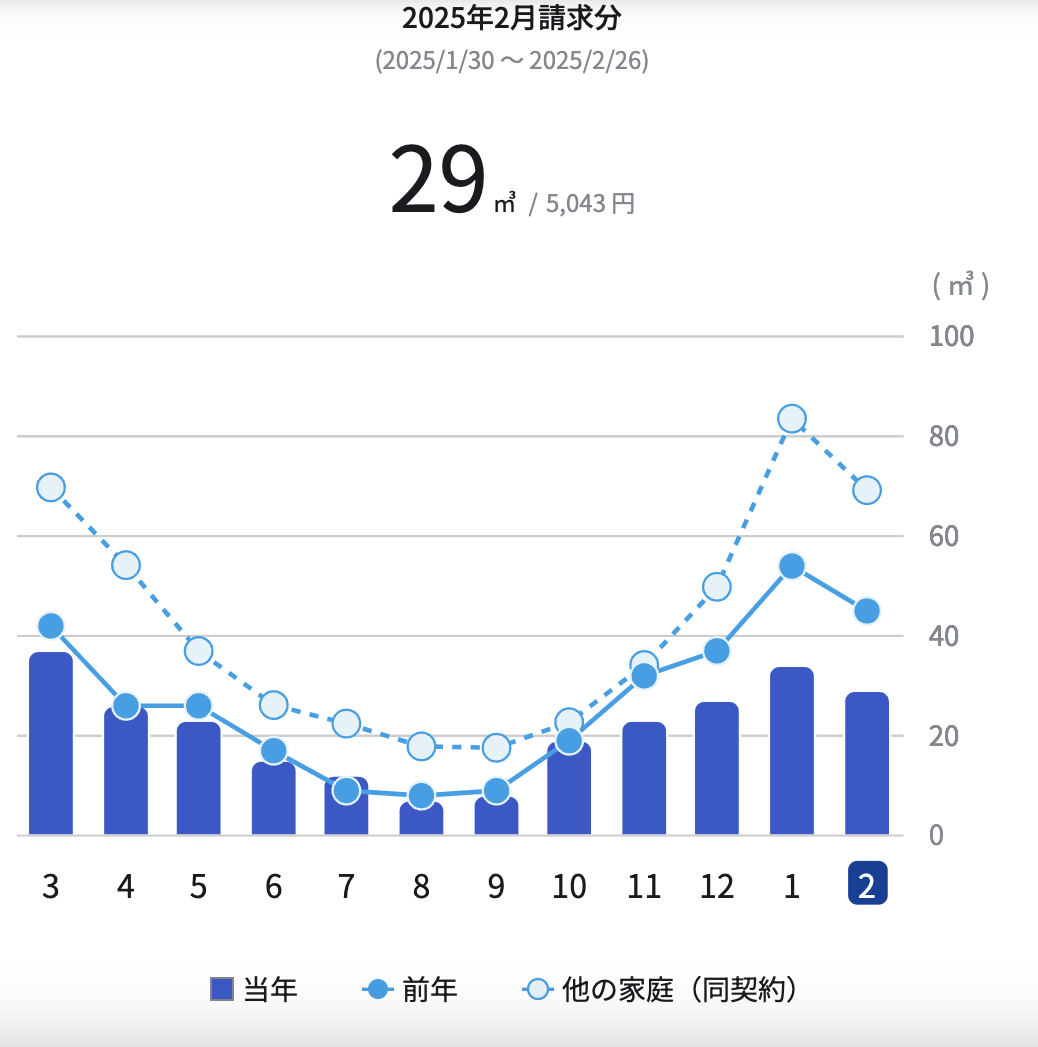

Easy mudlfat aquarium
東京で、トビハゼなどの汽水の生き物を、安く楽しく飼う方法を研究?しています。 東京はトビハゼの生息北限です。美しい干潟をいつまでも一緒に守りましょう。
I am currently in the process of developing an accessible method for maintaining a blackish-water aquarium in Tokyo cost-effectively.
Tokyo, situated within a northern subtropical region, represents the northern range limit for mudskippers.
I aspire to perpetually preserve the invaluable tidal flats.
魚類: トビハゼ 甲殻類:ユビナガホンヤドカリ、コメツキガニ 貝類:アサリかホンビノスガイ、アラムシロ、カワアイ、クチキレツノガイ
多足類:ゴカイ
初期費用 6,300円 水槽4,000円、ポンプ1,700円、塩分濃度測定600円 あとは餌代が、2ヶ月に一度300円程度。 アクリルカッター 800円
水棲ガニ ケフサイソガニなど。あまりに体格差があると、食べられるかもしれないが、どちらも3cmくらいの大きさであればお互い威嚇しあうくらいで食べ合う関係にはならない。いると水が綺麗になる。基本濾過食。
二枚貝 (ホンビノス・あさりなど) 水が綺麗になる
ホソウミニナ 張り合いがでる、藻を食べてくれる。(ただし土の表面) 水槽壁面の藻は食べてくれない。
多毛類 とにかく水が切になる。多毛類はすごい。そしてなかなか死なない。すごい。
アラムシロ よくトビハゼが威嚇している。アラムシロ
ヨコエビ ただ、あっという間に増えて困る。壁面の藻を綺麗にしてくれる。トビーが食べているかどうかは謎。
ユビナガホンヤドカリは、塩分濃度が高くなると、明らかに活動が落ちる(口元の水の動きが悪くなる)ので、塩分の指標になります。(塩分濃度があると、よく上の方に登ってくる、という動作も見せます) 抱卵すると、うちの水槽だと泥の上の方に登っているようにも見えます(要検証) 抱卵して成体で冬を越すのだそう。なんで。
オスはナワバリ意識が強く他の生物と喧嘩するので、地上を歩く生き物はあまり入れてあげないほうが良いかもです。張り合いがあるかもですが
カニがいるか、貝がいるか、で適した盛り方があったりする。
・真ん中に富士山 パターン
人間から見ると死角ができてしまうが、それがトビハゼにとって落ち着く場所になったりもする。 また、真ん中の山にカニを住まわすと良い。 カニはよく脱走を試みますが、真ん中の山にカニを住まわすと、周りをトビハゼがぐるぐる回るので、カニが外に出て行かないのである。 カニとトビハゼの睨み合いがよく発生するのでみていて楽しい。
・隅に山パターン
山があると、トビハゼやカニの脱走の手助けになってしまうが、少し湿り気の低い山があると、そこに大体カニが住む。 トビーも1日に数度、体を乾かしたり、山陰から獲物を狙うのを見ていると、山好きらしい。
・数ヶ所の潮だまりを作る
どのトビハゼも、何ヶ所か水たまりがあって、そこを行ったり来たりするのが一番楽しいようだ。 しばらく水たまりにいて、また別の水たまりに移動することで、いない間にエサとなる生き物が泥中から出てくるのを待つ作戦に見える。
・ちょっと水の深い部分を作る
トビハゼはどうやら近づいてくるのもの色や足音の方向で、鳥だ(地上の敵)と判別したり、大きな魚だ(水中の敵)と判別したりする。 基本的には足音の反対方向に逃げるのだが、割と色もよくみている。白っぽい格好をしていると鳥と判定するので、水の中に逃げたくなるし、黒っぽい格好をしていると大きな魚と判定するので、土の上に逃げていく。 そういう修正もあり、地上の敵から逃げたい時用の、少し水の深い水たまりを作ってあげると嬉しいようだ。
-トビハゼは、16度以下になると冬眠するとの文献あり。 -東京のマンションなので暖かく、真冬だと人がいると16度ほどまで下がって持ち堪えます(人がいない場合は13度あたりまで下がる)。しかし、16度切るので対策が必要です。
** 普通の方法 **
・まあこの程度の不足であれば、5Wか10Wのヒーターを水槽に入れるのが一般的で一番楽です。
** ランニングコスト・ゼロで、数ヶ月で元が取れる暖房。ただし、毎日時間を食われる **
・我が家では、トビハゼのいる居間に灯油用のポリタンクを5つほど用意し、そこに風呂の残り湯をポンプで汲んで入れています。 ・寝る前にトビハゼ水槽の近くに、2つほどタンクを設置し、薄い発泡スチロールや、ダンボールの覆いでカバーします。 ・朝になったら、覆いは取り外します。 ・事前に温度計で確認したところ、仕掛けてから7,8時間ほど+3度〜+5度を維持しています。特に19度以下あたりから下がりにくくなるのでとても有効です。 ・水槽は「レグラスフラットF-40S/B」12l。ここに、1/3ほどの泥と汽水を入れたものです。 ・ちなみにトビハゼ様も冬眠しなくなるだけでなく、部屋が朝まで暖かいので、朝床暖を入れる必要がなくなり、暖房費が浮きます。
** イニシャルコスト **
** 効果 **
1月2月と朝が寒い月でも床暖房入れることがなくなり、月¥4,000くらい浮きます。 でも毎日30分くらい時間を取られるので、これやったら1日百円払って暖房かけたほうがいいな、と思うこともよくあります。 国のため(エネルギー赤字対策)、自然のためにやってる、という謎の言い訳をしながら実施しています。 あと夜間暖房つけっぱなしにすると、トビハゼが欲しい温度よりも高くなってしまうので、トビーのためにも良いかなと
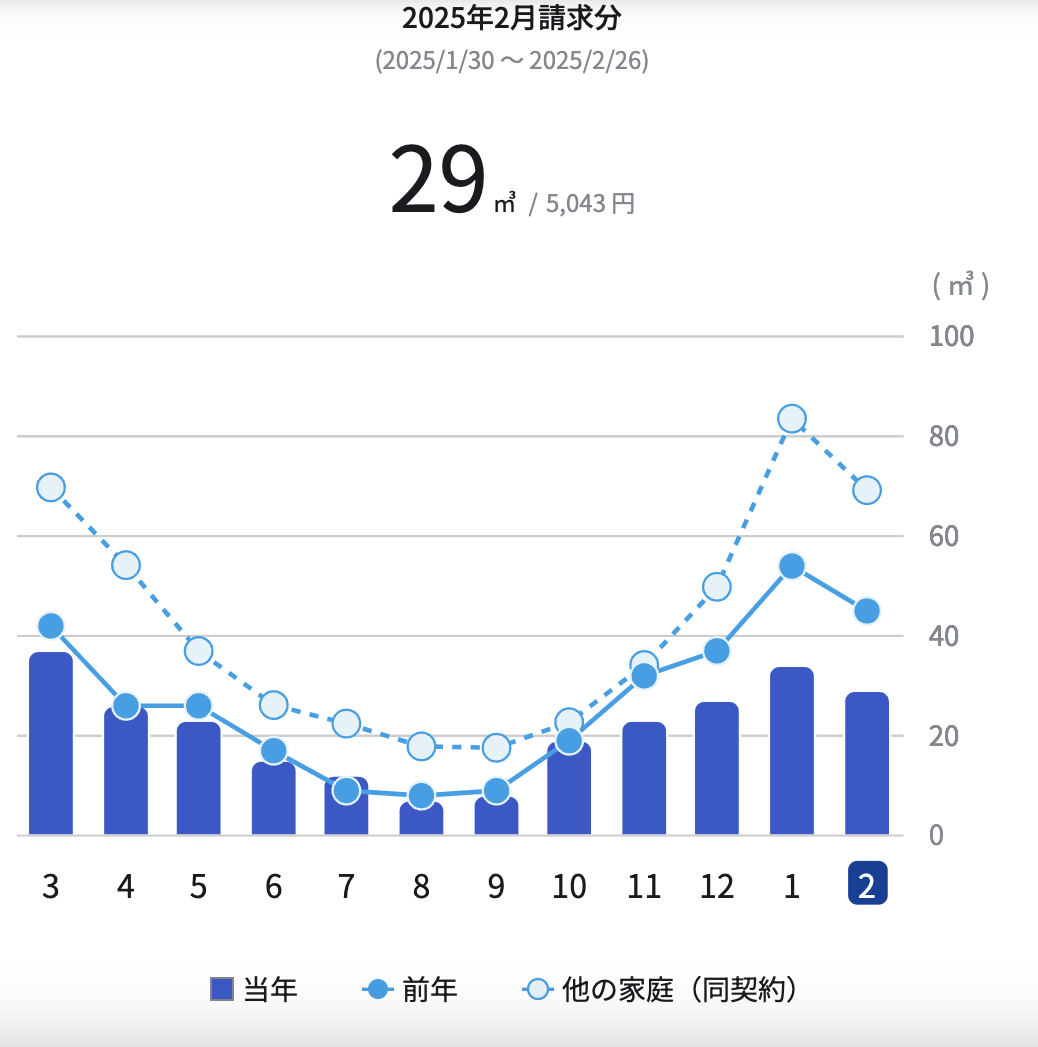

重いタンクを動かすので、持つときは腰を痛めないよう注意。灯油と違って、水は重たいです。いい運動にはなります。
・冬 1.023-1.025 ・夏 1.019-1.022
水の密度は、
| 温度 | 差分(対25度) | 密度 |
|---|---|---|
| 10 | +0.0026 | 999.741 |
| 15 | +0.0020 | 999.138 |
| 20 | +0.0010 | 998.233 |
| 25 | 0 | 997.062 |
| 30 | -0.0015 | 995.654 |
水の密度表詳細は、こちら ちなみに、水の粘度は ・4度付近は20度の約1.5倍 1.5 mPa/s ・95度では20度の約0.3倍 0.30 mPa/s
美しい水の方が長生きする説もありますが、海洋循環のモデルの1つPOMでは、懸濁態有機物質の重要性が説かれています。 病気やえらへの微生物付着による窒息の話もありますが、 トビハゼは皮膚呼吸ができるということや、 ・砂とか分解者が多くいそうなものを利用 ・貝類との共生 することで、より自然に近い形で飼うことができると考えています。
下記論文によると、マクロベントスへの栄養寄与率について、 下流域では、河川POM、海洋POMの寄与率が底生微細藻類もはるかに大きく、四季通して50−80%の寄与率とされています。 (陸上植物の死骸は10%程度) https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/264245/1/CoHHO_jp_03.pdf P.4
(江戸川放水路トビハゼ生息干潟の特性)[https://www.jstage.jst.go.jp/article/prooe1986/16/0/16_0_357/_pdf/-char/ja]
明治43年の大洪水を契機に江戸川放水路が作成された。
改修のため、数ヶ月間、トビハゼを飼育施設に移動させて、工事改修後戻している。
@2355toby